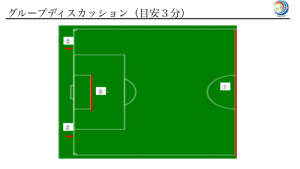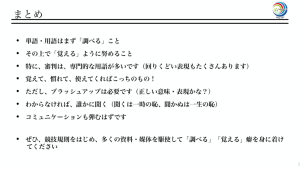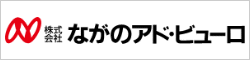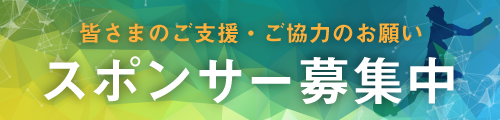2025年9月18日(木)第5回 長野県レフェリーアカデミーがオンラインで開催されました。
講義テーマは「審判(サッカー)にまつわる単語・用語」で小出貴彦さんが講師を担当しました。
今回の講義では、普段サッカーや審判に接する中でよく使われている単語・用語を受講生の皆さんと確認をしました。
事前テストでは、いくつかの単語・用語の意味を言語化してもらいました。
1 競技規則をどのくらい見て(開いて)いますか?
①一緒に過ごしている!(毎日)
②気になったらすぐ見て(開いている)(週1回以上)
③気になったらまとめて見ている(2週に1回程度)
④小テストのときは見て(開いて)いる 月1回以上
⑤あまり見ていない
多くの受講生の方が②もしくは③で定期的に見ていると回答しました。
例えば、、、
ゴールのクロスバーやクロスバー、フラッグポストなどは競技規則に記載されているので、分からなかったら調べてしっかりと正式名称を確認しましょう。
2 グループディスカッション
グループに分かれてフィールドのライン(①〜③)の名前を確認しました。
特に、③「ゴールラインに平行なゴールエリアのライン」は回答に悩んだ方が多くいました。
3 用語の確認
事前テストに出題された以下の用語の意味を確認しました。
ニアサイド
ファーサイド
センタリング(クロスボール)
ポストプレー
◇ファウル? ファール?どちらでしょうか?
⇒競技規則では、「Foul → ファウル」 とされています。
◇用語の中には、英語表現に言い換えている用語もあります。
例)
・つまずかせる → トリッピング
・押す → プッシング
・身体的接触によって相手競技者の進行を遅らせる → インピーディング
その他、「不用意」「無謀」「過剰な力」、「意図的なプレー」と「ディフレクション」、「SPA」「DOGSO」の用語の意味も確認をしました。
◇「タクティカルファウル」を実際の試合映像を見ながら意味の確認をしました。
フットサルでは競技規則で明記されており参考に例示しました。
(フットサル)「タクティカルな反則」
カウンターアタックや相手競技者が相手ゴールを攻撃するための時間とスペースを持っているときの可能性を防ぐための戦術として、競技者が意図的に行うファウル。
タクティカルファウルに対しては、注意は必要だが、すべてがイエローカードとは限らない。
4 まとめ
5 受講生の感想より
- フィールドの名前が分かったり、いろいろな人と話し合いができた。
- コーナーフラッグポストや任意のラインなど覚えていなかったものがあり、この講義で覚えることができました。
- テクニカルファウルはほぼ知らなかったので理解することができて良かったです。
- 知らない用語、単語の意味がよくわかった。SPAとDOGSOの違いがよくわかった。
- 様々な事象を映像などから具体的に自分の中に落としこんでいきたい。思い込みで判定を下すことがないよう正しい知識を常に持ち続けたい。
- これからの審判の活動の中でもっと理解を深めていかなければいけないと改めて思いました。競技規則をしっかり読んで審判をしていきたいです。
- 曖昧になっていた用語について、自分自身の中で再確認し整理できてとても有意義でした。
- 1度、原点に戻ることも大事ですね。
- 知らなかったことを教えていただきました。
- 任意のマークや、ゴールラインと平行なゴールエリアのラインなど知らない用語がかなりあったので勉強になった。
- 普段使ってる単語から聞いたことのない単語まで幅広く触れることができて、新たな気づきや、再確認につながりました。
- さらに競技規則に触れる機会を増やしていきたいと思います。
- 競技規則やサッカーに関する書籍等見て学習しようと思いました。
- 呼び方が決まってないラインについて、講義に取り入れて頂き、理解を深めることができました。
- まだまだ知識が足りないと感じています。と同時に体力の方も、年齢を言い訳にせず向上させていきたいと思います。